発表者: サイボウズ株式会社 安田智宏さん(iUG事務局メンバー) (文責:佐々木)
すでにグループウェアを活用している会社で社内ブログをやるとどうなるのか・・・「私個人の見解です」とお断りしながら事例を紹介してくれたのが、iUG事務局のメンバーでもあるサイボウズの安田さんです。
サイボウズ株式会社は1997年に創業したご存じグループウェアベンダー。従業員数は現在163名で、月に1度は全員が顔を合わせることのできる機会もあります。
加えて、当然ながら自社開発のグループウェアをフル活用。行動予定をスケジューラーに登録し、日報、掲示板と、安田さん曰く「過剰なぐらい」情報共有を行っています。
「情報共有のための社内ブログは不要」ともいえる環境でしょう。それでは、なぜ社内ブログを導入したのでしょうか。
社内ブログが導入されたのは2004年6月頃。当時管理部門で広報IRを担当していた社員が「管理部門から社内を変えていこう」という活動の一環として社内ブログを提案したことで始まりました。フリーのソフトをサーバーにインストールして、社内へはメールでの通知のみ。最初は発案者が直接声をかけた2~3名からスタートしたのだそうです。
派遣社員も含めた全員にアカウントを発行していますが、実際に全員が書いているわけではないとのこと。
プレゼンでは実際のエントリの内容も一部紹介されました。
- マーケティング担当者によるCM撮影の裏話
- 使い勝手の良いフリーソフト知りませんか
- 製品の名前が決まるまで
- 社長がある機会に社員から寄せられた疑問に個人的な考えを述べる
などなど、雑談に近いものから真剣なものまで、「(全員に通知される)掲示板に投稿するほどのもではないけれども」というエントリが並びます。
(ちなみにブログへのエントリーはグループウェアにRSS配信され、ブログポータルに近い形で最新エントリを閲覧することができます。別途個人でのRSS登録も可能です。)
そんなサイボウズさんの社内ブログですが、果たして評価はどうなのでしょうか。
「個人的な見解ですが」としつつ、安田さんは次のように整理していました。
- 社員が何気ない情報を発信するトレーニングになっている。「伝えるべき」情報ではなく「伝えたい」情報が発信されている。
- ないと困る「必需品」ではないが、あれば便利な「嗜好品」であり、有効に活用している人もいる。
- 書き手は少ないが、(実は)読み手は多い。掲示板は書き手が読み手を選ぶが、ブログは読み手が書き手を選ぶもの。
- 結果として、導入の目的「みんなが自由に考えていることを発信できる」は果たしている。「ナレッジ共有」のような事例も出てきている。
もっとも課題として、やはり「書く時間がない」「それは業務なのか」「書き始めたものの何を書いたらよいか分からない」といった意見もあるそうです。
一方でサイボウズさんでは社外向けの「社員ブログ」もスタートしており、社内では書いていないけれども社外向けには書いている「突き抜けた?」方もいるとのこと。自分の気持ちを書くことで、パートナーとのコミュニケーションにつながっている事例も生まれているようです。
「(成功か失敗か)一言で結論を出すのは難しいです。まだ結論を出すのは早いのかもしれません」と安田さん。
自身も社外向けのブログ「経営企画室 企画のもと」の他に社内ブログを書いており、実は今の経営企画室での仕事をするきっかけになったのは社内ブログだった、というエピソードも話してくれました。
ところで、この社内ブログはエントリの内容に制限のない「ノールール」。
「やりとりがエスカレートして仲違いが発生するようなトラブルはなかったのか」という質問が会場からありましたが、会社の規模の関係でいつでも顔を合わせることができることもあり、幸いにしてこれまでそういったことはなかったそうです。
サイボウズさんの事例は、いわゆる業務上の情報共有とは違った社内ブログの活用事例として参考になる面もあるのではないでしょうか。もっとも、それはすでに別の形で「情報共有ができている」という、ある意味恵まれた環境があってのことかもしれませんけどね。
 |
佐々木吾朗(ささき ごろう) ENIGMA VARIATIONS |

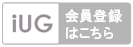

















コメント